脂質異常症(高脂血症)
脂質異常症(高脂血症)とは

血液中には脂質成分が含まれていて、主に中性脂肪(トリグリセライド)、LDLコレステロール(悪玉コレステロールといわれている)、HDLコレステロール(善玉コレステロールといわれている)の3要素で構成されていて、それぞれの脂質成分には正常値があります。
HDLコレステロールには細胞に蓄積した不要な脂質成分を除去して動脈硬化を予防する働きがありますが、LDLコレステロールが過剰に血液中に増加していくと血管内に沈着、蓄積して動脈硬化を進行させてしまいます。中性脂肪は、直接的には動脈硬化への影響はありませんが、中性脂肪が増加していくとLDLコレステロールの増加やHDLコレステロールの減少に影響を与えてしまいます。したがって、動脈硬化の進行度はLDLコレステロールが直接的に関わっていますが、HDLコレステロールや中性脂肪も間接的に関わっているので、それぞれの測定値を注意深く判断していく必要性があります。
ただし、中性脂肪に関しては食事の影響が強く反映されてしまうので、空腹時での血液検査が望ましいです。
脂質異常症とは、この脂質成分が正常値の範囲から逸脱した状態(異常値)が認められる場合に診断されます。以前は「高脂血症」と呼ばれていましたが、最近では病名が改変されて「脂質異常症」として呼ばれることが多いです。
脂質異常症の診断基準
- ①LDLコレステロール値は140mg/dl以上
- ②中性脂肪値(トリグリセライド)は150mg/dl以上
- ③HDLコレステロール値は40mg/dl未満
- ④LDLコレステロール/HDLコレステロール比(L/H ratio)は1.5以上
脂質異常症の症状
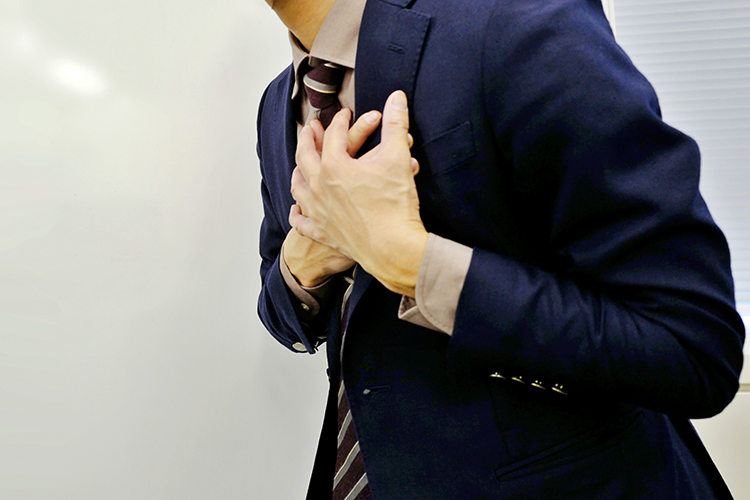
脂質異常症による症状は、目立った自覚症状として現れないことが多いです。
しかし、そのまま放置していると動脈硬化が進行し、心筋梗塞や狭心症、脳梗塞などの生命に関わる重篤な合併症を発症する可能性があります。また、中性脂肪値が高いと脂肪肝や急性膵炎などを発症するリスクが高くなるので注意が必要です。
脂質異常症による主な合併症
①脳梗塞
脂質異常症が原因で、脳内の血管に動脈硬化が進行することがあります。動脈硬化により血管が閉塞することで脳細胞が壊死して、重篤な脳梗塞などの合併症を引き起こします。
緊急性の高い病気で、適切な治療を受けないと後遺症や死亡の危険性があります。手足の痺れや麻痺・呂律困難・失語・視野の一部欠損・体のバランス失調などの症状が現われます。
②狭心症や心筋梗塞
脂質異常症が原因で、心臓の血管に動脈硬化が進行することがあります。心臓には冠動脈といわれる、正常に心臓を作動させるための大切な細い血管があります。動脈硬化が進行すると、その血管自体が脆くなりやすく、冠動脈が狭窄や閉塞をおこすことで心筋細胞が壊死して、重篤な狭心症や心筋梗塞などの合併症を引き起こします。発症した場合は生命の危険性があるので、緊急性が高く適切な治療が必要となります。胸痛・胸部違和感・胸部圧迫感・背部痛などの様々な症状が現われます。
脂質異常症の原因
脂質異常症の原因は生活習慣の乱れによる影響が大きいといわれています。
食生活の乱れや運動不足をはじめ、肥満、喫煙、ストレスなどが原因で成人以降に発症することが多いです。その他にも、甲状腺機能低下症、糖尿病や高血圧症などによる合併症、遺伝的要因、ステロイド剤等の長期服用などの影響により引き起こされることもあります。
体型が瘦せ型で脂質異常症と診断された場合は、遺伝的要因の可能性があります。
各脂質成分が影響する原因の一覧
LDLコレステロール値(悪玉コレステロール)が高い原因
動物性脂肪やコレステロールの高い食品を多く摂取している可能性があります。
- ①肉の脂身や惣菜などの揚げ物類
- ②バターやマーガリン、チーズなどの乳製品
- ③鶏卵や魚卵
- ④お菓子やパン類、インスタント食品やハム、ソーセージなどの加工食品
中性脂肪値(トリグリセライド)が高い原因
脂肪や糖質の高い食品を多く摂取している可能性があります。
- ①ジュースや果物、砂糖菓子などの甘い食品
- ②ビールなどのアルコール類
- ③他、運動不足や喫煙など
HDLコレステロール値(善玉コレステロール)が低い原因
不健康な食生活による肥満や運動不足、喫煙などの生活習慣の乱れが原因といわれています。
- ①お菓子やパン類、インスタント食品やハム、ソーセージなどの加工食品
- ②他、運動不足や喫煙など
治療
脂質異常症治療の基本は、『まずは食事と運動』がよく知られています。
食事療法
動物性脂肪やコレステロールの高い食品(肉脂身、揚げ物、乳製品、卵など)や、糖質の高い食品(ジュース、お菓子、アルコール類など)を中心とした食生活を見直して、動脈硬化を予防する生活習慣に改善していきます。
(注意するポイント)

- ①間食や夜食は控えて、栄養バランスの良い食事を心がける
- ②大豆類(豆腐、納豆など)や魚介類の食生活に切り替える
- ③野菜や海藻類、きのこ類など食物繊維の豊富な食材を摂取
- ④植物性油で調理をする
- ⑤果物の食べ過ぎには注意する
- ⑥アルコール類の飲み過ぎには注意する(原則として禁酒)
禁煙指導

喫煙は血液中のHDLコレステロール(善玉コレステロール)を減少させる作用があり、結果としてLDLコレステロール(悪玉コレステロール)が増加することで動脈硬化が進行していく危険性があります。そのため、節煙や禁煙の指導が必要となります。
運動療法

運動により体の筋肉量が増えることで、基礎代謝が上がり肥満の予防につながります。
さらに、中性脂肪を減少させてHDLコレステロールを増加させる効果があるといわれているので動脈硬化の予防にもつながります。また、動脈硬化はストレスでも進行するといわれているので、運動でストレスを発散することは効果的かと思われます。大切なのは、無理せずにご自身の体調に合わせた運動を継続することです。
(注意するポイント)
- ①ウォーキングや散歩など身近な運動から始める
*慣れてきたら早歩きやジョギングなど強度を上げる - ②無理せず体調や天気の良い時だけでも運動する
- ③自身の体力に合わせた運動を継続する
目安:一日30分以上の有酸素運動を毎日
薬物療法
食事や運動などの生活習慣の見直しをしても、脂質成分の改善が認められない場合は飲み薬による治療を行います。脂質異常症の薬には中性脂肪値を下げる薬やLDLコレステロール値を下げる薬など様々な種類があるので、それぞれご自身の脂質成分の状態に合わせた飲み薬を処方します。
脂質異常症に有用性のある主な検査
血液検査

血液検査では血液中の脂質の値を調べることができます。脂質異常症の診断は血液中の脂質の値によってなされるため、診断のためには血液検査が必要です。また、脂質異常症の原因となる甲状腺機能などの検査も行っていきます。
- 頸動脈超音波検査
首の左右の動脈(頸動脈)を観察することで、血管内の内中膜複合体(IMC)の肥厚具合やプラーク(コレステロールの塊)の付着による狭窄度、血流速度の評価など、動脈硬化の進行度が判断されます。脳卒中や脳梗塞の原因となる動脈硬化を判断するためによく選択される検査です。さらに頸動脈を観察することで全身の血管状態も推定・把握するのに役立つともいわれています。 - ABI検査(足関節上腕血圧比)
上腕と足関節の血圧を測定して、動脈硬化の進行度や血管年齢を調べます。
特に、閉塞性動脈硬化症の診断によく選択される検査です。
脂質異常症による様々な合併症のリスク判定にも役立つ検査です。 - 心電図検査および心臓超音波検査
脂質異常症による動脈硬化の影響で、心臓にも動脈硬化が進行することがあります。
狭心症や心筋梗塞など生命の危険性がある重篤な心臓疾患を引き起こす可能性があります。
心電図や心臓超音波の検査では、心臓内部の情報を画像で詳細に可視化できるので、狭心症や心筋梗塞をはじめ、動脈硬化による弁膜症の進行度などを判断するのにも役立ちます



大川医院院長 大川 修(おおかわ おさむ)
- 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医
- 日本消化器病学会認定 消化器病専門医
- 日本肝臓学会認定 肝臓専門医
- 日本消化器内視鏡学会認定 消化器内視鏡専門医
- 日本医師会認定 産業医


