肝機能障害とは
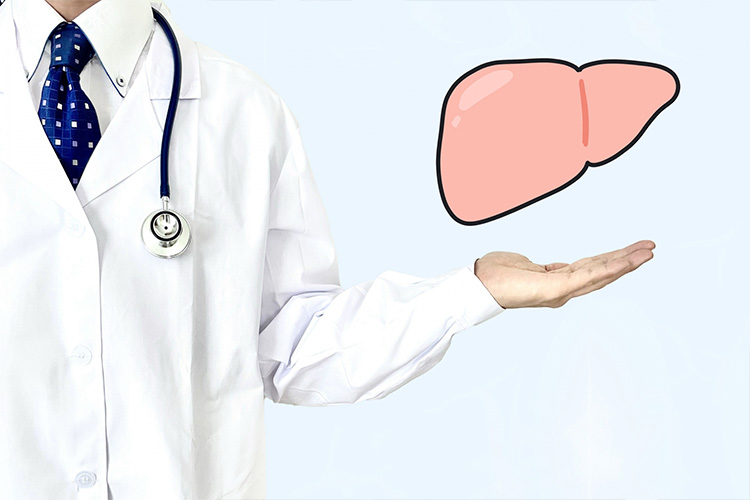
肝臓は、人間の体内にある臓器の中で最も大きなもので、お腹の右上、肋骨の下あたり(右季肋部)に位置しています。成人の場合、その重さはおよそ1,200gから1,500gにもなり、全身の代謝や解毒に関わる、生命維持に欠かせない臓器です。
肝臓の働きとその重要性
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれることがあるように、多少の障害があっても初期には症状が出にくい特徴があります。しかし、その機能は非常に多岐にわたっており、人間が健康に生きるために必要不可欠な臓器です。主な役割は以下の3つに分類されます。
①代謝(たいしゃ)
肝臓は、食事から吸収された栄養素(糖質・脂質・タンパク質など)を処理して、体が使えるエネルギーや物質へと変換します。たとえば、ブドウ糖をグリコーゲンという形で蓄えたり、タンパク質から必要なアミノ酸を作ったりするのも肝臓の仕事です。
②解毒(げどく)
肝臓は、体にとって有害な物質を分解・解毒して体外に排出しやすい形にする働きも担っています。たとえば、アルコールや薬物、食品添加物、古くなったホルモンなどを分解するのは肝臓です。
③胆汁(たんじゅう)の生成
肝臓では、「胆汁」という消化液が作られており、これは脂肪を消化・吸収するために欠かせません。胆汁は肝臓から胆のうを経て腸へ送られ、食べた脂肪を効率よく分解します。
肝機能障害とは何か?
こうした多くの重要な役割を持つ肝臓ですが、何らかの原因でこれらの機能が低下してしまう状態が「肝機能障害」です。肝機能が障害されると、体内に老廃物や毒素がたまりやすくなり、全身にさまざまな影響を及ぼす可能性があります。
初期のうちは自覚症状がほとんどないため、健康診断などで行われる血液検査(肝機能検査)によって初めて異常が見つかるケースも少なくありません。たとえば、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、ALP、ビリルビンなどの数値をチェックすることで、肝臓の状態を知ることができます。
肝機能障害の主な原因
脂肪肝(しぼうかん)
脂肪肝は、肝臓の細胞に中性脂肪が過剰に蓄積した状態です。アルコールをたくさん飲む人に多い「アルコール性脂肪肝」と、飲酒をほとんどしない人でも発症する「非アルコール性脂肪肝疾患(NAFLD)」があります。
近年では、肥満や糖尿病、高血圧、高脂血症などの生活習慣病が背景にある「非アルコール性脂肪肝炎(NASH)」が注目されており、放置すると肝硬変や肝がんに進行することもあります。
ウイルス性肝炎
肝炎ウイルス(A型・B型・C型など)に感染することで起こる肝炎です。特にB型肝炎ウイルス(HBV)やC型肝炎ウイルス(HCV)は、慢性化しやすく、肝硬変や肝がんのリスクが高いとされています。感染経路は血液や体液、母子感染などさまざまです。
ウイルス性肝炎は早期発見・早期治療が重要であり、定期的な検査とウイルスマーカーのチェックが推奨されます。
肝機能障害の早期発見と予防の重要性

肝臓は、かなりのダメージを受けるまで症状が出にくい臓器です。そのため、「症状が出てから受診」ではなく、定期的な健康診断や血液検査によって肝機能の異常を早期に見つけることが、将来的な重篤な疾患を防ぐカギになります。
特に、次のような方は注意が必要です:
- アルコールをよく飲む
- 肥満や糖尿病などの生活習慣病がある
- 薬やサプリメントを複数使用している
- 肝炎ウイルスに感染したことがある
- 家族に肝疾患の方がいる
こうしたリスクのある方は、定期的な肝機能検査と医師の診察を受けることが強く推奨されます。
脂肪肝とは
脂肪肝とは、肝臓の細胞(肝細胞)の中に中性脂肪が過剰に蓄積してしまっている状態を指します。具体的には、肝臓を構成する肝細胞の5%以上に脂肪が溜まっている状態と定義されています。
通常、肝臓にはある程度の脂肪が存在していても問題はありませんが、体内に不必要な脂質や糖質が多くなると、それらが肝臓で中性脂肪へと変換され、やがて脂肪が過剰に蓄積するようになります。これが脂肪肝のはじまりです。
また、多量の飲酒も脂肪肝を引き起こす大きな原因のひとつです。アルコールの代謝過程では大量の中性脂肪が生成されるため、過剰な飲酒を続けることで肝臓に脂肪が蓄積しやすくなるのです。
日本国内では、特に中高年の男性を中心に脂肪肝が多く見られており、日本人男性の約4割が脂肪肝と診断されているともいわれています。その背景には、日常的な過食・運動不足・偏った食生活などの生活習慣の乱れによる肥満が大きく関係しています。
肥満でなくても脂肪肝になる?
「脂肪肝は太っている人の病気」と思われがちですが、実際には体型が痩せていても脂肪肝になることがあります。
一般的に、BMI(体格指数)が25kg/m²以上の場合は「肥満」と診断されますが、BMIが正常範囲(18.5〜24.9)の方でも内臓脂肪が多い“隠れ肥満”型で脂肪肝を発症するケースがあるのです。
また、内臓脂肪型肥満を中心としたメタボリックシンドローム(内臓肥満、高血圧、高血糖、脂質異常などが組み合わさった状態)とも深い関係があり、脂肪肝は生活習慣病の“はじまり”とも言える状態です。
放置は危険!脂肪肝がもたらす合併症とは?
脂肪肝は、初期にはほとんど自覚症状がないため、気づかないうちに病状が進行していることも少なくありません。しかし、放置すると次のような深刻な病気につながる可能性があります。
肝硬変(かんこうへん)
肝臓の細胞が繰り返しダメージを受けることで、徐々に硬くなり、機能が低下してしまう状態です。肝硬変になると、回復は非常に困難になります。
肝がん(肝細胞がん)
脂肪肝や肝硬変が長期にわたり持続すると、やがて肝がんへと進行することもあります。
糖尿病の発症・悪化
脂肪肝はインスリンの効き目(インスリン感受性)を低下させ、血糖値のコントロールが難しくなるため、2型糖尿病の発症や悪化につながります。
脂質異常症・動脈硬化
脂肪肝を抱える方は、血中の中性脂肪やLDL(悪玉)コレステロールが高くなる傾向があり、動脈硬化を進行させる要因になります。これは将来的な心筋梗塞や脳梗塞といった命に関わる病気にも関係してきます。
このように、脂肪肝は「放っておいても大丈夫な病気」ではなく、生活習慣病の前兆や、より重篤な病気への入り口としてとらえ、しっかりと対処する必要があります。
自覚症状がほとんどないのが特徴
脂肪肝の厄介な点は、症状がほとんど現れないことです。
「体がだるい」「食欲がない」などの漠然とした体調不良を感じることもありますが、これらは他の病気と区別がつきにくく、脂肪肝が原因とは気づきにくいのが実情です。
そのため、多くの方は健康診断での血液検査や腹部エコー(超音波検査)によって初めて脂肪肝が発見されることになります。
肝機能の異常値(AST、ALT、γ-GTPの上昇)や、肝臓に脂肪が沈着して白っぽく見える超音波検査の画像所見などが診断の手がかりになります。
したがって、無症状だからといって油断せず、年に1回の健康診断を継続的に受けることが脂肪肝の早期発見・重症化予防に直結します。
脂肪肝の分類
脂肪肝には、その原因によって大きく2つのタイプがあります。原因に応じて治療方針も異なりますので、それぞれの特徴を理解することが大切です。
①アルコール性脂肪肝
過度の飲酒が原因で脂肪が肝臓に蓄積している状態を「アルコール性脂肪肝」と呼びます。アルコールを代謝する過程で大量の中性脂肪が作られ、それが肝細胞に蓄積されることで発症します。
このタイプの脂肪肝は、飲酒を控えることで改善が期待できる一方で、放置して飲酒を続けると「アルコール性肝炎」→「肝線維化」→「肝硬変」→「肝がん」と進行するリスクがあります。
肝臓は再生能力が高い臓器ですが、それにも限界があります。進行してしまう前に、節度ある飲酒または禁酒によって肝臓への負担を減らすことが最も重要です。
②代謝機能障害関連脂肪性肝疾患(MASLD)
③代謝機能障害関連脂肪肝炎(MASH)
近年では、飲酒歴がないにもかかわらず、肥満・糖尿病・脂質異常症などの生活習慣病を背景に発症する脂肪肝が注目されています。このような病態は、従来「非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)」と呼ばれていましたが、現在では国際的に用語が改訂され、「代謝機能障害関連脂肪性肝疾患(MASLD)」と呼ばれています。
MASLDは、そのままにしておくと肝臓に慢性的な炎症が起こり、やがて代謝機能障害関連脂肪肝炎(MASH)へと進行します。MASHでは、肝臓の細胞が破壊されたり線維化が進んだりすることで、最終的に肝硬変や肝がんといった重篤な病気に至るリスクがあります。
MASLD・MASHは、アルコールをほとんど飲まない人でも発症することから、「誰でもなり得る肝疾患」とされており、日本では推定約200万人がMASHを発症しているといわれています。
この背景には、現代社会における食生活の乱れ(高脂肪・高糖質食)、運動不足、ストレスなどの要因が大きく関係しており、脂肪肝は単なる肝臓の問題ではなく、生活習慣全体の見直しが必要な“警告サイン”と捉えるべき疾患です。
脂肪肝の治療
脂肪肝の治療の基本は、「食事」と「運動」の見直しです。
つまり、日々の生活習慣を改善することで、脂肪肝の進行を食い止め、肝機能の正常化を図ることが最も効果的な治療方法となります。早期の段階から適切な生活改善に取り組み、脂肪の蓄積を抑えるとともに、原因となる生活習慣病(高血圧、糖尿病、脂質異常症など)の管理を行うことが大切です。
脂肪肝治療における「食事療法」「運動療法」「薬物療法」の3つの柱について詳しく説明します。
食事療法

脂肪肝の予防と改善には、まず栄養バランスの取れた食生活の実践が欠かせません。
過剰なカロリー摂取や脂質、糖質のとりすぎは、中性脂肪の増加を招き、肝臓への脂肪の蓄積を助長してしまいます。
控えたい食品・習慣
- 動物性脂肪が多く含まれる食品(バター、ラード、霜降り肉など)
- コレステロールが高い食品(レバー、卵黄、内臓系の肉類)
- 甘い食品・飲み物(ジュース、菓子パン、スナック菓子、果物の過剰摂取)
- アルコール類(特にビールや日本酒など糖質を含む酒類)
- 飽和脂肪酸やトランス脂肪酸が多い食品(ファストフード、マーガリン、加工食品など)
脂肪肝の改善には、こうした食品をなるべく避け、一日三食を規則正しく、腹八分目を意識した食事を心がけることが大切です。
脂肪肝におすすめの食品
- 大豆製品(豆腐、納豆、味噌など)→植物性タンパク質が豊富で、動物性脂肪の代替にもなる
- 魚介類(特に青魚)→DHA・EPAといった良質な脂質が含まれ、脂質代謝をサポート
- 野菜・海藻・きのこ類→食物繊維が豊富で、コレステロールや糖の吸収を抑える
- 植物性油(オリーブオイル、菜種油など)→飽和脂肪酸を減らし、不飽和脂肪酸を積極的に摂取できる
また、塩分や糖分を控えた薄味の料理を心がけることも重要です。過剰な塩分摂取は高血圧を助長し、糖質のとりすぎは脂肪肝や糖尿病を悪化させます。
さらに、禁煙・禁酒を意識することも、肝臓への負担軽減に大きな効果があります。とくにアルコール性脂肪肝の方は、完全な禁酒が治療の第一歩となります。
運動療法

脂肪肝の大きな原因のひとつが「肥満」です。とくに内臓脂肪型肥満(メタボリックシンドローム)があると、脂肪肝を発症しやすくなります。
そのため、無理のない適度な運動を継続することが、肝臓の脂肪を減らすために非常に効果的です。
運動のメリット
- 肝臓に蓄積した脂肪を燃焼する
- インスリン抵抗性を改善し、糖尿病予防に役立つ
- コレステロールや中性脂肪を下げる
- 心肺機能を向上させ、全身の代謝を促進する
- ストレス解消にもつながり、自律神経の安定にも貢献
運動療法のポイント
以下のような内容で、日常生活に取り入れやすい運動からスタートしましょう。
- ウォーキングや散歩など、手軽な有酸素運動から始める
- 慣れてきたら、早歩きや軽いジョギングに強度を上げていく
- 自分の体調や生活スタイルに合わせて無理なく継続
- 一日30分以上の運動を、週3回以上を目安に実践
「毎日きっちり運動しなければ」と思うとハードルが高くなりますが、「晴れた日の買い物を徒歩にする」「休日に公園を散歩する」など、身近な工夫で“動く習慣”をつくることが大切です。
薬物療法

食事療法や運動療法を数ヶ月実践しても改善が見られない場合や、すでに生活習慣病を合併しているケースでは、薬物療法が選択されることがあります。
ただし、脂肪肝そのものを治すための特効薬は現時点では存在しません。
そのため、薬物療法では主に脂肪肝の背景にある生活習慣病(高血圧、糖尿病、脂質異常症など)を適切にコントロールすることが治療の中心になります。
ウイルス性肝炎とは
日本国内でウイルス性肝炎を引き起こす主な原因は、B型肝炎ウイルス(HBV)とC型肝炎ウイルス(HCV)による感染です。報告によると、日本のウイルス性肝炎の約90%が、この2つのウイルスによって引き起こされているといわれています。
ウイルス性肝炎の感染経路と感染リスク
B型・C型肝炎ウイルスは、主に血液を介して感染するウイルスです。
- 過去の輸血や血液製剤の使用(とくに1980年代以前)
- 不衛生な鍼治療や刺青(タトゥー)
- 使い回された注射器や医療器具の使用
- 性行為による感染(主にB型)
- 母子感染(出産時などに母親から子どもへ)
近年では、輸血や血液製剤のチェック体制が非常に厳しくなったことにより、感染のリスクは大幅に減少しています。しかしながら、性行為による感染や母子感染など、日常生活に関わる形での感染リスクは今なお存在するため、正しい知識と予防意識が大切です。
ウイルス性肝炎は自覚症状が乏しい病気です
ウイルス性肝炎の怖いところは、初期にはほとんど自覚症状が現れない点です。
多くの方が、以下のような形で初めて異常を知ることになります。
- 健康診断や人間ドックでの血液検査(肝機能の異常値)
- 別の疾患で受けた検査での偶然の指摘
- 肝臓の腫れを指摘された画像検査(エコーやCTなど)
病状が進行すると、以下のような症状が出現することがありますが、いずれも曖昧で「肝臓が原因」と気づかれにくいものです。
- 倦怠感(だるさ)
- 食欲不振
- 腹部の不快感や膨満感
- むくみ
そのため、「自覚症状がない=安心」ではないということを理解し、定期的に健康診断を受けることが非常に重要です。
ウイルス性肝炎が疑われたらどうする?
健康診断や検診で「肝機能異常」や「ウイルスマーカー陽性」などを指摘された場合は、速やかに消化器内科などの医療機関を受診することが大切です。
医療機関では、より詳しい血液検査・ウイルスマーカー検査・画像検査・必要に応じて肝生検などを行い、原因となるウイルスの有無や肝臓の状態を正確に評価します。
ウイルス性肝炎の治療
A型肝炎ウイルス(HAV)
A型肝炎は主に汚染された食べ物や水から感染し、急性の肝炎を引き起こすタイプです。通常は自然に治癒し、慢性化することはありません。
しかし、発熱・食欲不振・嘔吐などの症状が強く出ることもあるため、必要に応じて薬物療法(対症療法)を行うことがあります。
B型肝炎ウイルス(HBV)
B型肝炎は、一部の人で慢性肝炎へと移行するタイプのウイルスです。ウイルスの活動が活発な場合には、抗ウイルス薬(核酸アナログ製剤など)を用いてウイルスの増殖を抑制する治療が行われます。
ただし、現在の医学ではウイルスを完全に除去することは難しいとされており、治療の目的は、肝臓へのダメージを最小限にとどめ、肝硬変や肝がんへの進行を防ぐことにあります。
また、HBV感染の予防にはワクチン接種が有効であり、医療従事者や感染リスクの高い方には積極的に推奨されています。
C型肝炎ウイルス(HCV)
C型肝炎は、かつては慢性化しやすく治療が難しい病気とされていましたが、近年は新しい内服治療薬の登場により、大きく治療成績が向上しています。ウイルスの完全除去(著効率95%以上)も期待できるようになりました。治療期間は従来のインターフェロン療法に比べて短く、副作用も軽減されているため、多くの患者さんにとって負担の少ない治療が可能です。
現在では、C型肝炎の治療目標は「ウイルスの完全除去」です。早期に治療を行うことで、肝硬変や肝がんのリスクを大幅に下げることができます。

大川医院院長 大川 修(おおかわ おさむ)
- 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医
- 日本消化器病学会認定 消化器病専門医
- 日本肝臓学会認定 肝臓専門医
- 日本消化器内視鏡学会認定 消化器内視鏡専門医
- 日本医師会認定 産業医


